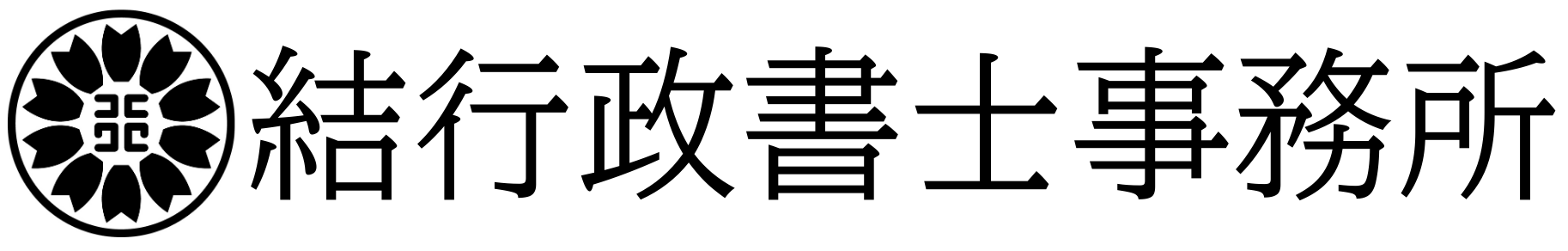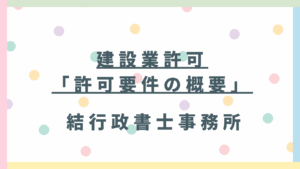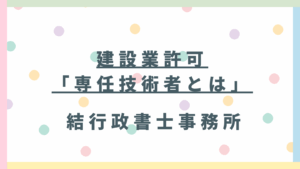建設業許可のキーパーソン!「経営業務の管理責任者」を行政書士が徹底解説
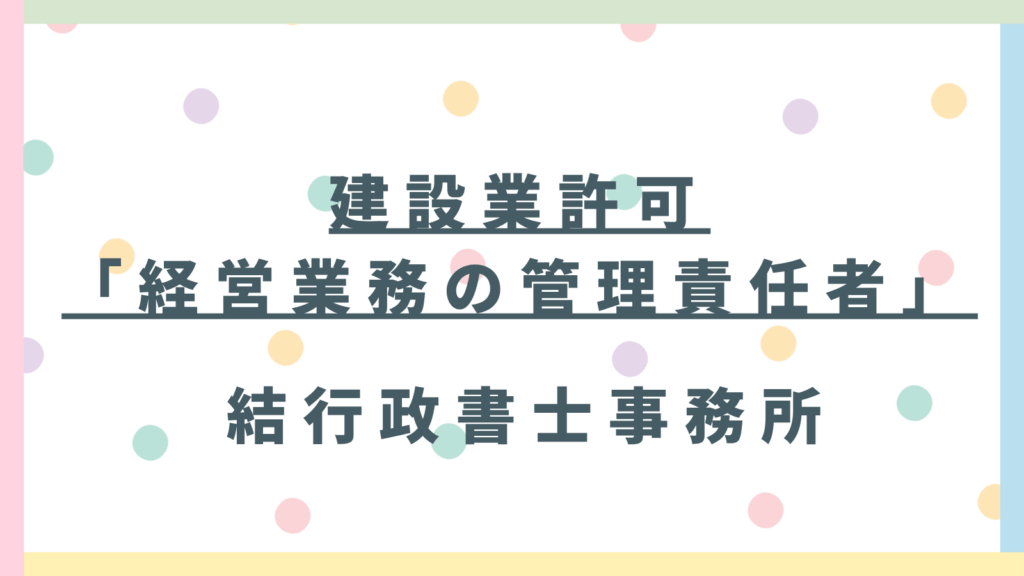
こんにちは!埼玉県東松山市で建設業許可申請を行っている結行政書士事務所です。
建設業許可の取得を検討されている事業者様にとって、しばしば「難しい」「複雑」と感じられるのが、この「経営業務の管理責任者(通称:経管)」の要件です。事業の健全な運営に欠かせない、まさに「会社の顔」とも言える重要なポジション。この要件をクリアできるかどうかが、許可取得の大きなカギを握ります。
今回は、この「経営業務の管理責任者」について、行政書士の視点から分かりやすく、そして詳しく解説していきます。あなたの会社がこの要件を満たせるのか、一緒に確認していきましょう。
経営業務の管理責任者(経管)って、どんな人?なぜ必要なの?
目次
「経営業務の管理責任者」とは、簡単に言うと「建設業の経営を適切に運営できる経験と能力を持った人」のことです。建設業は、発注者の財産に関わる重要な工事を請け負うため、その事業が適切に管理されていることが、社会的な信頼を得る上で不可欠だからです。
許可審査において、審査員は「経管」を通じて以下の点を確認します。
- 事業の継続性と安定性: 過去の経営経験から、会社を安定的に運営し続けられるか。
- 経営リスクへの対応力: 予期せぬ事態にも適切に対応し、事業を軌道修正できるか。
- 法令遵守への意識: 建設業法など関連法規を理解し、適正な経営を行えるか。
この「経管」は、会社の規模や工事の種類に関わらず、すべての建設業許可で必須の要件です。
あなたは「経管」になれる?主要な要件をチェック!
経営業務の管理責任者として認められるには、建設業法第7条第1号イまたはロのいずれかの経験が必要です。
1. 建設業で5年以上の役員経験がある人【建設業法第7条第1号イ】
最も一般的なパターンがこれです。過去に、建設業を営む法人で取締役などの役員、または個人事業主として、5年以上経営業務を経験している人が該当します。
ポイント:
- 「役員経験」とは、単なる肩書きではなく、実際に会社全体を指揮・監督する立場にあったことを指します。
- 例:株式会社の代表取締役、取締役、合名会社・合資会社の無限責任社員、合同会社の業務執行社員、NPO法人の理事など。
- 「建設業を営む」とは、その会社が建設業許可を持って実際に建設工事を行っていたか、または許可がなくても軽微な建設工事を継続して行っていたかが問われます。
- 証明書類: 経験期間を証明するために、登記簿謄本、確定申告書、工事請負契約書などの提出が求められます。
2. 無許可会社での役員経験も認められるケース
「これまで建設業許可を持っていなかった会社で役員をしていたけれど、それでも経管になれるの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
実は、建設業許可を持たない会社(いわゆる無許可業者)での役員経験でも、一定の条件を満たせば「経営業務の管理責任者」としての経験として認められる場合があります。
ポイント:
- 「建設業を営む」という要件は、必ずしも「建設業許可を持っている会社」に限定されません。
- 軽微な建設工事を継続して行っていた実績: 許可が不要な「軽微な工事」(1件の請負代金が500万円未満など)であっても、その会社が継続的に建設工事を請け負い、事業として行っていたことが重要です。
- 経営業務への関与: その無許可会社において、あなたが実際に経営業務(資金調達、契約、人事など)に携わっていたことを証明できる必要があります。
- 証明書類: 登記簿謄本、確定申告書(事業内容が建設業とわかるもの)、工事請負契約書、請求書、入金記録など、具体的な工事実績と経営への関与を示す客観的な書類が求められます。
3. 準ずる地位で5年以上の経営業務執行経験がある人【建設業法第7条第1号イ】
役員ではないけれど、それに「準ずる地位」で、5年以上建設業の経営業務を執行した経験がある人も認められます。
ポイント:
- 「準ずる地位」とは、役員等から具体的な権限を委譲され、その権限に基づいて、対外的な取引など経営業務を総合的に管理・執行していた立場を指します。
- 例:支店長、営業所長、事業部長、工場長など、その部門全体の経営判断を任されていたポジション。
- 役員等に代わって実質的に経営判断を行っていた実績が求められます。
- 証明書類: 組織図、職務分掌規程、辞令、給与明細、具体的な業務内容を説明する書類など、権限が委譲されていたことを示す資料が必要になります。
4. 経営業務管理責任者の経験を補佐できる人がいる場合(2年以上)【建設業法第7条第1号ロ】
特定の条件下では、上記の「5年以上の経験」が満たせなくても、常勤役員等のうち1人が以下のいずれかに該当し、かつ、その常勤役員等を直接に補佐する者がいる場合も認められることがあります。この要件は、2020年の建設業法改正で追加された比較的新しいものです。
ポイント:
- 常勤役員等のうち1人が以下のいずれかに該当する必要があります。
- 建設業に関し、2年以上の役員等(※)の経験を含む5年以上の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理または業務運営のいずれかの業務を担当する者に限る)としての経験を有する者(建設業法第7条第1号ロ⑴)
- 建設業に関し、2年以上の役員等(※)としての経験を含む5年以上の役員等の経験を有する者(建設業法第7条第1号ロ⑵)
- (※)ここでの「役員等」は、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、または相談役・顧問その他名称を問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を指します。
- 「適切な補佐体制」とは、その経験を補佐する者が、財務管理、労務管理、業務運営の全ての管理業務について、5年以上の実務経験を持つ人である必要があります。補佐する者は、当該業者における5年以上の財務管理、労務管理、業務運営の業務経験のいずれかを有する必要があります。また、これらの経験を有していれば、補佐者は1名でも問題ありません。
- このルートは複雑なため、専門家への相談が推奨されます。
「経管」に関するよくある疑問・注意点
Q1. 私自身が社長だけど、他の会社での経験でもいいの?
A. はい、現在の会社の経験だけでなく、過去に別の建設業者の役員や個人事業主として経験があれば、その期間もカウントできます。ただし、その期間の勤務状況や業務内容を証明できる書類が必要です。
Q2. 途中で業種が変わったり、ブランクがあったりしたらどうなる?
A. 基本的には途切れずに継続した経験が求められます。ただし、建設業に関連する事業(例:建設コンサルタントなど)の経験が一部認められるケースや、ブランクの理由によっては個別に判断される場合もあります。ご自身のケースに不安がある場合はご相談ください。
Q3. 「常勤」ってどういうこと?
A. 原則として、会社の営業時間中に、その事務所に常駐していることを指します。他の会社の役員や従業員と兼任している場合などは、常勤と認められないことが多いです。
Q4. 経験を証明する書類がない場合は?
A. 経験を証明する客観的な書類(登記簿謄本、確定申告書、工事請負契約書、請求書など)が最も重要です。もし書類が不足している場合は、追加の証明方法や、状況によっては許可取得が難しいケースもあります。事前に確認が必要です。
まとめ:「経管」の要件クリアで、建設業許可への道を開く!
「経営業務の管理責任者」の要件は、建設業許可取得の第一関門とも言える重要なポイントです。ご自身の経験や、会社の主要な人材がこの要件を満たしているかを確認することが、許可申請の最初のステップとなります。
要件の判断や必要書類の準備は、非常に複雑で専門知識を要します。「うちの会社は大丈夫かな?」「どうやって証明したらいいんだろう?」など、少しでも不安を感じたら、迷わず専門家にご相談ください。
東松山市の結行政書士事務所では、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、「経営業務の管理責任者」の要件クリアに向けた最適なアドバイスと、複雑な申請手続きのサポートをさせていただきます。
あなたの事業が、建設業許可という「パスポート」を手にし、さらなる成長を遂げられるよう、私たちがお手伝いします。どうぞお気軽にご連絡ください。