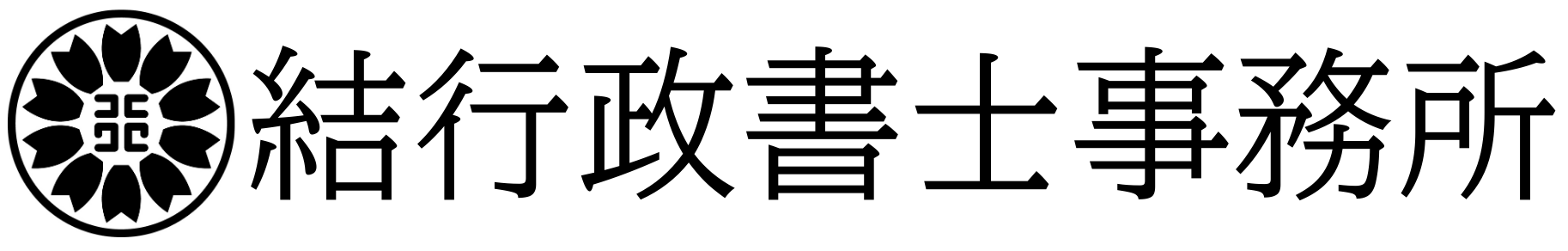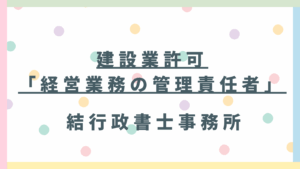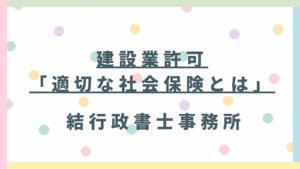建設業許可のキーパーソン!「専任技術者」の要件を徹底解説
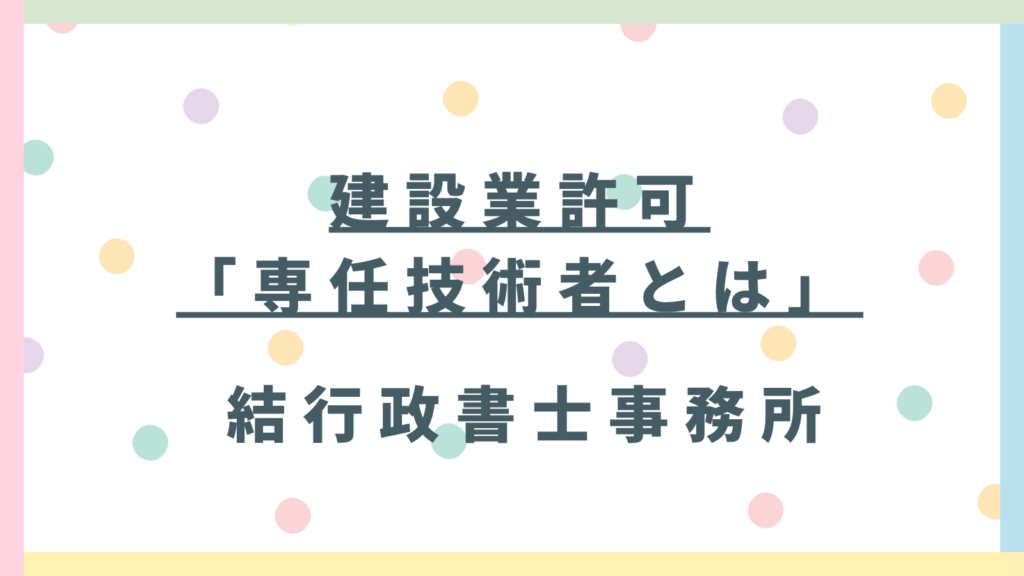
こんにちは!埼玉県東松山市で建設業許可申請を行っている結行政書士事務所です。
建設業許可の取得を目指す事業者様にとって、「経営業務の管理責任者(経管)」と並んで、しばしば疑問の声が上がるのが「専任技術者」の要件です。建設工事のプロフェッショナルとして、現場を適切に管理・監督するために不可欠な存在である専任技術者。この要件をクリアできるかどうかが、許可取得のもう一つの大きなカギとなります。
今回は、この「専任技術者」について、行政書士の視点から分かりやすく、そして詳しく解説していきますね。あなたの会社がこの要件を満たせるのか、一緒に確認していきましょう。
専任技術者ってどんな人?なぜ必要?
目次
「専任技術者」とは、簡単に言うと「建設工事に関する専門知識と実務経験を持ち、その技術を適切に管理・指導できる人」のことです。建設業法第7条第2号において、建設業の許可を受けるための要件の一つとして、各営業所に専任技術者を置くことが義務付けられています。これは、工事の適正な施工を確保し、品質や安全性を保つために不可欠だからです。
許可審査では、専任技術者を通じて以下の点を確認します。
- 技術的な専門性: 申請する建設工事の種類に見合った専門知識と技術力があるか。
- 実務経験: 過去の工事経験から、現場を円滑に進められるだけの経験があるか。
- 適正な施工管理: 法令を遵守し、品質の高い工事を行えるか。
この専任技術者は、会社の規模や工事の種類に関わらず、すべての建設業許可で必須の要件ですよ。
あなたは「専任技術者」になれる?主要な要件をチェック!
専任技術者として認められるには、建設業法第7条第2号イ、ロまたはハのいずれかの要件を満たす必要があります。大きく分けて「資格」または「実務経験」のいずれかです。
1. 指定学科を卒業し、一定期間の実務経験がある人
以下のいずれかに該当する者を専任技術者としています。
指定学科を卒業し、一定期間の実務経験がある人
建設関連の指定学科を卒業している場合、実務経験の期間が短縮されます。具体的な期間は、下記の通りです。
- 高校または中等教育学校の指定学科卒業者: 卒業後、申請する建設工事の種類に関して5年以上の実務経験。
- 大学または高等専門学校の指定学科卒業者: 卒業後、申請する建設工事の種類に関して3年以上の実務経験。
ポイント:
- 指定学科: 建設業法施行規則第7条第2号に定められた学科(例:土木工学科、建築学科など)であることが必要です。ご自身の卒業学科が該当するか確認しましょう。
- 証明書類: 卒業証明書、単位取得証明書、実務経験を証明する書類などが必要です。
2. 10年以上の実務経験がある人、または国家資格を持っている人
資格や指定学科の卒業がなくても、申請する建設工事の種類に関して、10年以上の実務経験があれば、専任技術者として認められます。
一般建設業においては、建設業法第7条第2号ハで規定される特定の国家資格を有する方もこの要件を満たすものと解釈されます。
ア.10年以上の実務経験がある人(建設業法第7条第2号ロ関連)
申請する建設工事の種類に関して、10年以上の実務経験を持つケースです。
ポイント:
- 経験内容: 単に工事現場にいた、というだけでなく、実際にその工事(例えば、内装仕上工事なら内装仕上工事)に直接関わっていたことが重要です。具体的な工事内容や期間を証明する必要があります。
- 証明書類: 工事請負契約書、注文書、請求書、施工台帳など、客観的に実務経験を証明できる書類が必要です。
イ.国家資格を持っている人(建設業法第7条第2号ハ関連)
建設業の業種に応じた特定の国家資格を持っている場合です。
主な資格の例:
- 土木工事業・建築工事業:一級・二級建築士、一級・二級土木施工管理技士、一級・二級建築施工管理技士 など
- 電気工事業:第一種・第二種電気工事士、電気主任技術者 など
- 管工事業:管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者、消防設備士 など
ポイント:
- 業種との関連性: 取得したい建設業の業種と資格の関連性が重要です。例えば、建築士の資格で土木工事業の専任技術者にはなれません。
- 特定建設業の場合: 特定建設業の許可では、後述の通り、より高度な技術力が必要とされるため、一級の資格や、指定された複数の一級資格など、より厳しい条件が課されます。
3. 特定建設業における専任技術者の要件(より高度な技術力)【建設業法第15条】
特定建設業の許可を取得する場合、専任技術者にはさらに厳しい要件が課せられます。これは、大規模な工事や下請け契約を多く行うため、より高い技術力と管理能力が求められるからです。
具体的な要件は、下記の通り規定されています。
- 国家資格の場合:
- 取得したい業種に対応する一級国家資格を持っていること(例:一級建築士、一級建築施工管理技士など)。
- 指導監督的実務経験を有する者:
- 一般建設業の専任技術者の要件を満たした上で、2年以上の指導監督的実務経験(発注者から直接請け負った工事で、政令で定める額(現在4,500万円)以上の建設工事について、主任技術者または監理技術者としての経験)が必要です。※指導監督的実務経験とは建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を指します。この経験は、発注者から直接請け負った工事に関するものに限られ、発注者側の経験や下請負人としての経験は含まれません。
- 国土交通大臣が認定した者:
- 上記に準ずる者として、国土交通大臣が認定した者が該当します。
ポイント:
- 特定建設業の専任技術者の要件は非常に厳しく、該当する方が少ない傾向にあります。ご自身のキャリアが該当するか、慎重な確認が必要です。
「専任」ってどういうこと?重要な常勤要件!
「専任技術者」の「専任」とは、「その営業所に常勤し、他の業務と兼務せずに専らその業務に従事すること」を意味します。
重要なポイント:
- 常勤性: 原則として、会社の営業時間中に、その事務所に常駐していることが求められます。他の会社の役員や従業員との兼任は認められません。
- 事業所の専任: 複数の営業所がある場合、それぞれの営業所に専任技術者を置く必要があります。一人の専任技術者が複数の営業所を兼任することはできません。
- 例外: ごく稀に、同じ会社の複数の営業所が近接しており、実態として兼務が認められるケースもありますが、これはあくまで例外的な判断となるため、基本的に避けるべきです。
専任技術者に関するよくある疑問・注意点
Q1. 実務経験を証明する書類がない場合は? A. 最も重要なのは客観的な書類(工事請負契約書、注文書、請求書、施工台帳など)です。もし書類が不足している場合は、追加の証明方法や、状況によっては許可取得が難しいケースもあります。事前の確認が必須です。
Q2. 資格は持っているけど、実務経験が足りない…? A. 資格と実務経験は、どちらか一方を満たせば良いケースと、両方が求められるケースがあります。ご自身のケースでどちらが必要か、正確な判断が必要です。
Q3. 親会社の経験でも認められる? A. 建設業の許可は法人単位で取得するため、子会社で許可を取得する場合、親会社の経験を専任技術者の実務経験として利用することは原則できません。ただし、具体的な資本関係や指揮命令系統によっては認められるケースもありますので、個別に確認が必要です。
Q4. 経営業務管理責任者と兼任できる? A. はい、一人が「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の両方の要件を満たす場合は、兼任が可能です。中小企業ではよくあるパターンです。
まとめ:専任技術者の要件クリアで、建設業許可への道を拓く!
「専任技術者」の要件は、建設業許可取得の重要なステップです。ご自身の資格や実務経験がこの要件を満たしているかを確認することが、許可申請の最初のステップとなります。
要件の判断や必要書類の準備は、非常に複雑で専門知識を要します。「うちの会社は大丈夫かな?」「どうやって証明したらいいんだろう?」など、少しでも不安を感じたら、迷わず専門家にご相談ください。
東松山市の結行政書士事務所では、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、「専任技術者」の要件クリアに向けた最適なアドバイスと、複雑な申請手続きのサポートをさせていただきます。
建設業許可取得への第一歩を、一緒に踏み出しましょう!